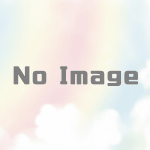ラダーの申し子! 嘉陽 来歴 新入幕まで
大学卒業後は二所ノ関部屋に入門し、2022年5月場所で三段目最下位(90枚目)格付出しで初土俵を踏んだ。初土俵の場所は6勝1敗であり、続く7月場所と9月場所は5勝2敗とし、入門4場所目の同年11月場所で幕下に昇進した。この場所は6勝 ...
ラダーの申し子! 嘉陽 来歴 入門前まで
嘉陽は沖縄県那覇市出身で中村部屋所属であり、年齢は25歳である。また身長171センチ、体重174キロであり、突き、押しを得意としている。
千葉県市川市生まれであり、市川市立新井小学校3年次から市川市相撲教室に通って稽古 ...
ラダーの申し子! 嘉陽 2025年3月場所13日目の草野戦
この場所は東十両2枚目で迎えていた。そして対戦相手の草野は前日に十両優勝を決めており、しかもここまで12戦全勝ということで新十両で初となる全勝優勝への期待が高まっていた。
相撲は当たってすぐに草野が右を差そうとしたが嘉 ...
ラダーの申し子! 嘉陽 ラダーとは?
ラダーとは縄ばしごのことである。縄ばしごを敷き、またいで跳ぶことで下半身強化や神経系からの筋肉への指令を発達させるトレーニングである。そして嘉陽は横への動きが持ち味の力士である。よってラダートレーニングはうってつけだと思っている。私 ...
歴史をつないだ男! 栃大海 最後に
2025年5月場所は新入幕の場所だったが4勝11敗の大敗に終わった。序盤は3勝1敗と白星が先行したものの、その後は連敗が止まらなくなってしまった。また内容的にも突き押しが通用せず、力量差があったと言わざるを得ない。また微妙な一番もあ ...
歴史をつないだ男! 栃大海 師匠の存在
師匠の春日野親方は元関脇・栃乃和歌である。和歌山県海南市(旧海草郡下津町)出身で春日野部屋所属だった。また身長190センチ、体重162キロであり、右四つ、寄り、上手投げを得意としていた。箕島高校から明治大学に進学した。そして1985 ...
歴史をつないだ男! 栃大海 部屋の稽古に関して
部屋の稽古を見て驚いたのが、当時入幕したばかりの遠藤が出稽古に来ており、栃ノ心に軽々と吊り上げられていたことである。写真を見て同じ幕内力士でもここまで力の差があるのかと驚いた記憶がある。おそらくスタミナの差が吊り技となって表れたと私 ...
歴史をつないだ男! 栃大海 部屋の紹介
所属する春日野部屋は1925年5月場所に現役を引退した出羽海部屋所属の横綱・栃木山が引退に伴って春日野を襲名して養父の部屋を継承した。そして今年で創設100周年ということで4月29日に春日野部屋創設100周年パーティーが開催された。 ...
歴史をつないだ男! 栃大海 元関脇碧山の岩友親方に関して 現役時代
また碧山は元幕内久島海の田子ノ浦部屋に入門しており、2012年に田子ノ浦親方が急逝後、春日野部屋に移籍した。そして転籍もまとめての転籍ではなく、当時の北の湖理事長から田子ノ浦部屋の一人一人に希望する移籍先を伝える封筒が届いたようだ。 ...
歴史をつないだ男! 栃大海 元関脇碧山の岩友親方に関して 歴史をつないだ功績
2023年5月場所に栃ノ心が引退した時点で碧山は部屋唯一の現役関取となった。しかしこの時点で年齢は35歳であり、衰えが懸念されていた。そして同年9月場所は東前頭14枚目で5勝10敗と負け越し、11月場所で十両に陥落した。これにより春 ...